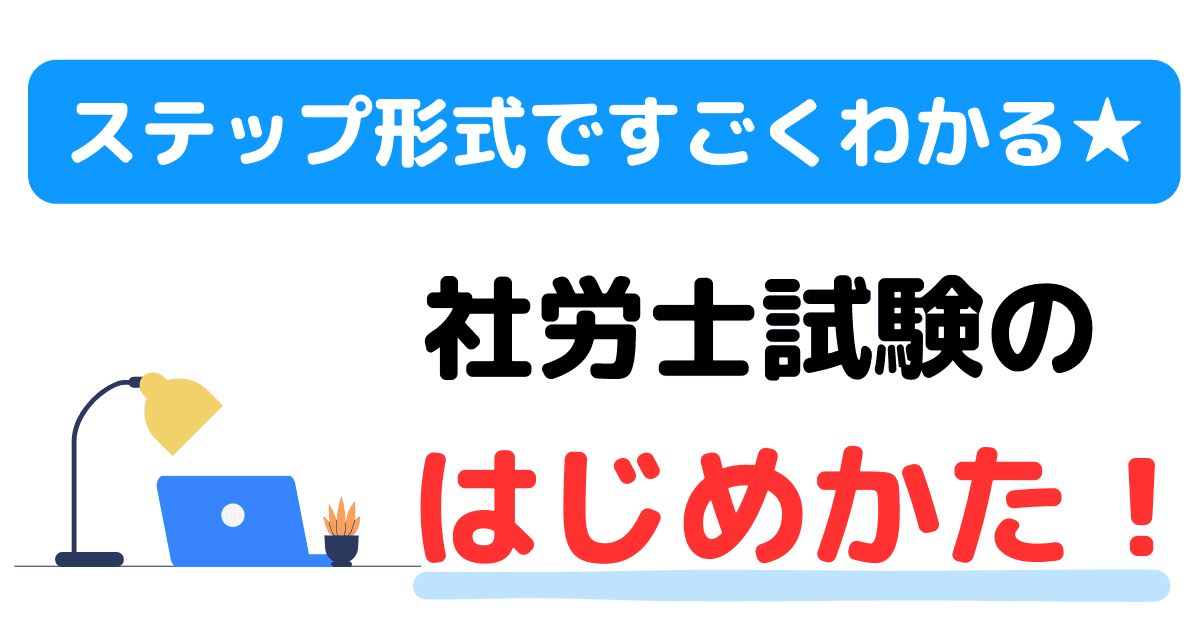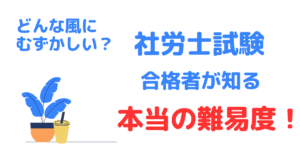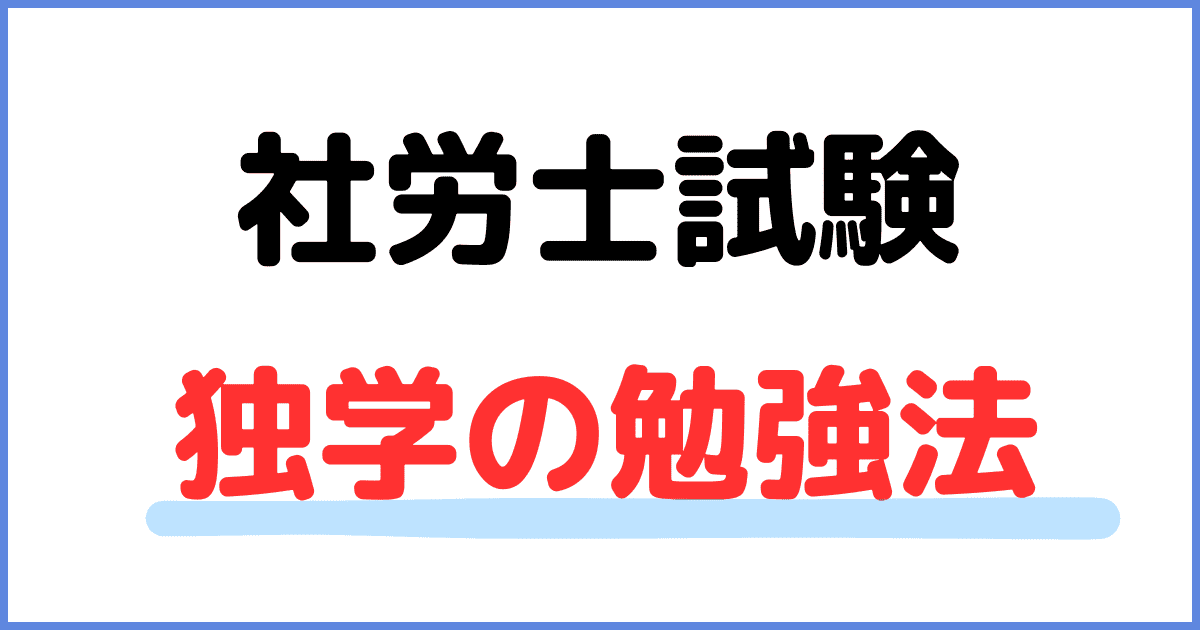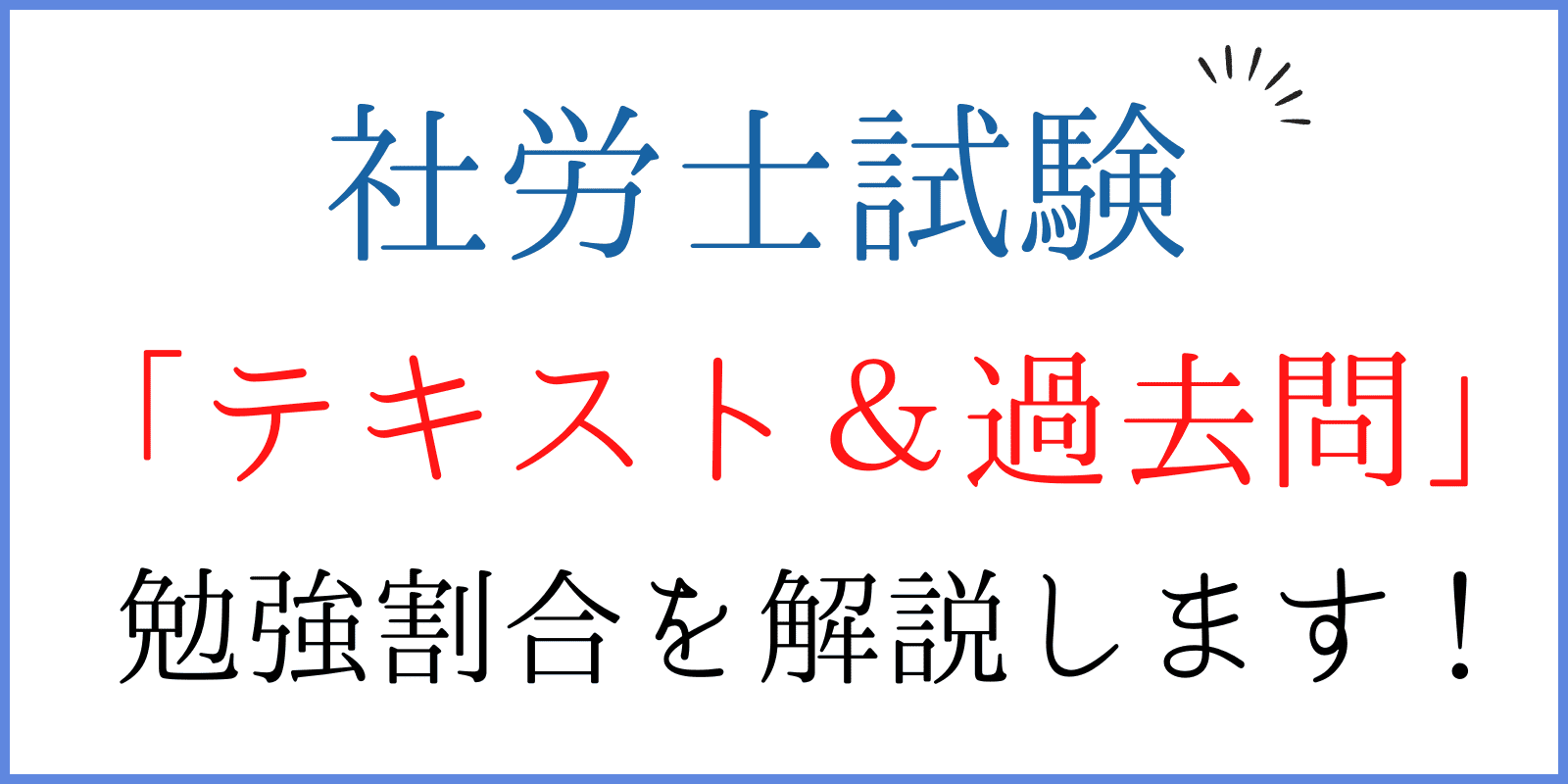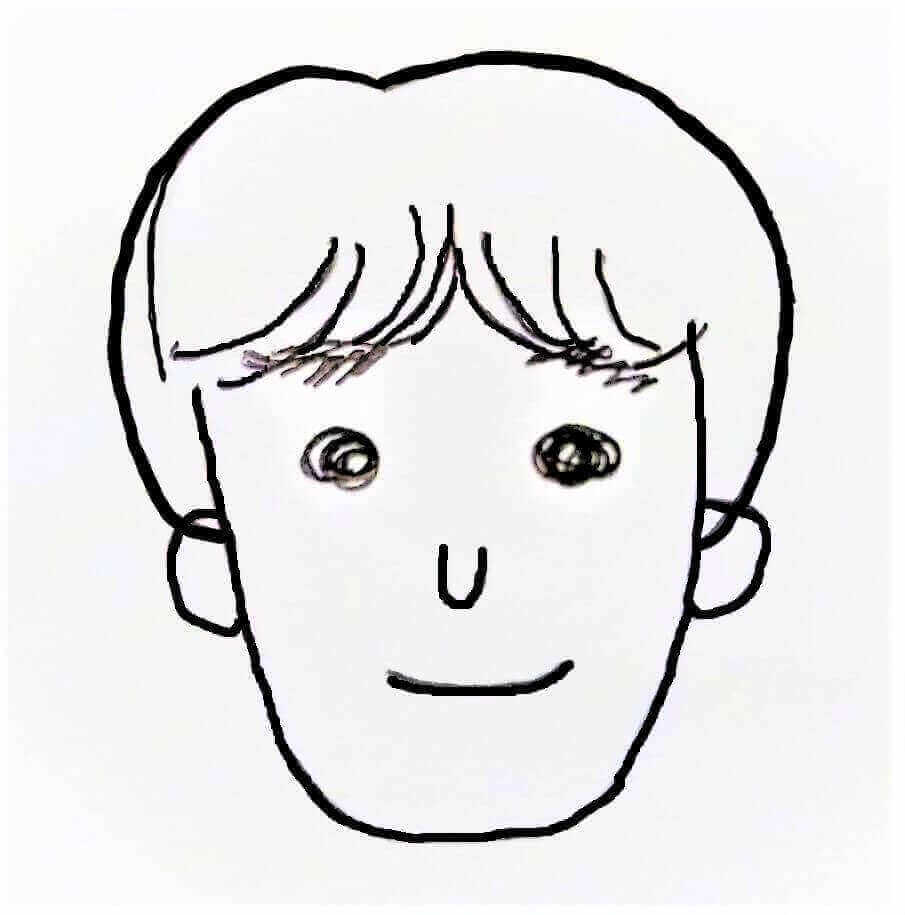- 社労士試験勉強割合(テキスト&過去問)

この記事でわかること!
テキストと過去問の勉強割合はどのくらいにしたほうが良いの?
今回は、私が社労士試験に合格するまでに「感じたこと・思ったこと」など、複数回の受験経験から気づいたことを書いていきます。
独学で合格した「実体験」から、テキストと過去問の勉強割合をお伝えします!
1【独学合格した実体験】社労士テキストと過去問の勉強割合を解説!
最初に結論をお伝えすると、過去問重視で勉強すべきです!
ここからは、簡潔に書くのでさらっと流し読みでわかります。
では、さっそく。
※過去問重視ではありますが、テキスト読み込みもすごく重要です!
労働基準法
・テキスト 3割
・過去問 7割
社労士テキストと過去問の勉強割合
テキストは勉強初期のころに2~3回読み込めば、あとは過去問をひたすら解くことで得点アップにつながる。過去問を中心に勉強したら、テキストはまちがえた過去問の該当箇所を確認する程度で十分。
労働安全衛生法
・テキスト 2割
・過去問 8割
社労士テキストと過去問の勉強割合
テキストの読み込みはほとんど必要なしで、選択式対策としてテキストを勉強するくらいと割りきる。テキストの読み込みに時間をかけても、択一式の得点にそれほど反映されない代表科目である。
労働者災害補償保険法
・テキスト 4割
・過去問 6割
社労士テキストと過去問の勉強割合
労災法はある程度しっかりとテキストを読み込む必要がある。保険給付がメインであり、業務災害や通勤災害など似たような用語も多数あり。テキストで用語の整理をしたあとで、過去問メインで問題を解きまくるのが効果あり!
雇用保険法
・テキスト 5割
・過去問 5割
社労士テキストと過去問の勉強割合
雇用保険法はテキストをしっかりと読み込むのが必要な科目。出題のメインは失業等給付関連だけど、給付の種類が多いので『まずは全体像を理解する』ためテキストの熟読が必要となる。この科目は過去問とテキストを常にセットにして勉強するのが得点アップに繋がる。
労働保険徴収法
・テキスト 4割
・過去問 6割
社労士テキストと過去問の勉強割合
労働保険徴収法はテキストをしっかりと読み込むことが効果的。概算保険料や確定保険料など、類似用語が多数あり整理をするためにもテキストでしっかりと覚えること。用語の整理ができたら、あとはひたすら過去問を解きまくれ!
労務管理その他の労働に関する一般常識
・テキスト 5割
・過去問 5割
社労士テキストと過去問の勉強割合
テキストと過去問をどれだけやっても得点に結びつかない代表科目。テキストや過去問から選択式でポッと出題される可能性があるので、勉強する割合をそれぞれ半分とした。しかし、じっくりと勉強する科目でないのは明らかで、択一式対策よりも『選択式対策』としてテキスト読み込みや時事問題に取り組みがけっこう大切な科目。
健康保険法
・テキスト 3割
・過去問 7割
社労士テキストと過去問の勉強割合
ここは思い切って過去問重視でいきたい。テキストでは被保険者の届け出関係とか、暗記すべきものはテキストでしっかりと勉強する。高額療養費などの難解な問題は『過去問』を解いてテキストで整理するのが効率的。けっこう過去問で得点できる可能性が高い科目。
国民年金法
・テキスト 6割
・過去問 4割
社労士テキストと過去問の勉強割合
国民年金は厚生年金の基礎知識となる。だからテキストの読み込みでしっかりと理解することが大事。最近は、本試験では実務的な問題が多くなっているから、テキストでしっかりと勉強して年金の基礎知識を付ける必要がある。
厚生年金保険法
・テキスト 4割
・過去問 6割
社労士テキストと過去問の勉強割合
国民年金でしっかりとテキストの読み込みができれば、厚生年金も国民年金と同じような用語が多いから、テキストの勉強は国民年金より少なくて十分。あとは過去問を解いていくことで、厚生年金法は実力アップができる。そして同時に国民年金の理解も相乗効果でアップできる。
社会保険に関する一般常識
・テキスト 3割
・過去問 7割
社労士テキストと過去問の勉強割合
テキストの3割は選択式対策として読み込み、過去問の7割は択一式対策とする。択一式は国民健康保険、後期高齢者、介護保険など出題される範囲は狭く、過去問ベースの勉強で十分対応できる。
2 テキスト&過去問 勉強割合一覧表
先ほどのテキスト&過去問について、勉強割合を一覧でまとめました。
下記をテンプレートとして、勉強割合を参考にするのも良いと思います。
✔ 勉強割合 一覧
| 科目 | テキスト | 過去問 |
| 労働基準法 | 3割 | 7割 |
| 労働安全衛生法 | 2割 | 8割 |
| 労働者災害補償保険法 | 4割 | 6割 |
| 雇用保険法 | 5割 | 5割 |
| 労働保険徴収法 | 4割 | 6割 |
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 5割 | 5割 |
| 健康保険法 | 3割 | 7割 |
| 国民年金法 | 6割 | 4割 |
| 厚生年金保険法 | 4割 | 6割 |
| 社会保険に関する一般常識 | 3割 | 7割 |
上記は、1つの例として、あなたにとって「今、必要と思う勉強割合」はどのくらい必要なのか、実際に数値を入れてみてください。
勉強割合を決めないで「テキストや過去問を勉強する」より、一覧表を作って自分なりの基準を作れば気持ちが楽になります。
あとは、勉強の進捗状況によって割合は変わってきますが、数字を随時入れるだけで目標ができます。
3 まとめ(テキストと過去問の勉強割合)
試験に合格するために必要なことは、問題を解く能力をあげることです。
実際、社労士試験に合格した受験生は「過去問」を中心に勉強している方が多いはずです。※ただ、私は「テキストの読み込み」も非常に重要な勉強法だと思っています。
受験生の目標は試験に合格することなので、ほかの人に教えられるほど詳しくなるのは合格後のことです。
いまは、自分の勉強割合を決めて、必要最低限のことを実践して、1年でも早く合格を目指すことが大切です。
テキスト&過去問の勉強割合で迷っているなら、当記事でお伝えした内容をぜひ参考にしてもらればと思います。
応援しています!
独学で受験するのは不安という方は、資格の大原を検討してみてはいかがですか?
資格の大原は「社労士24」など、合格実績は非常に高くなっています。社労士試験は独学より「予備校」を活用することで効率的な学習を可能にしてくれます。
⇩
勉強方法など不安な方はプロの指導もあります
-
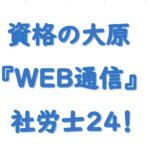
-
【必見!社労士24】資格の大原時間の達人シリーズ(2025料金)
資格の大原社労士24 (料金等)2025年受験対策 資格を取りたいと考えている方なら、だれもが知っているのが「資格の大原」です! 当記事では、大原の社労士講座の中でも、特に受講者が急増し ...
続きを見る