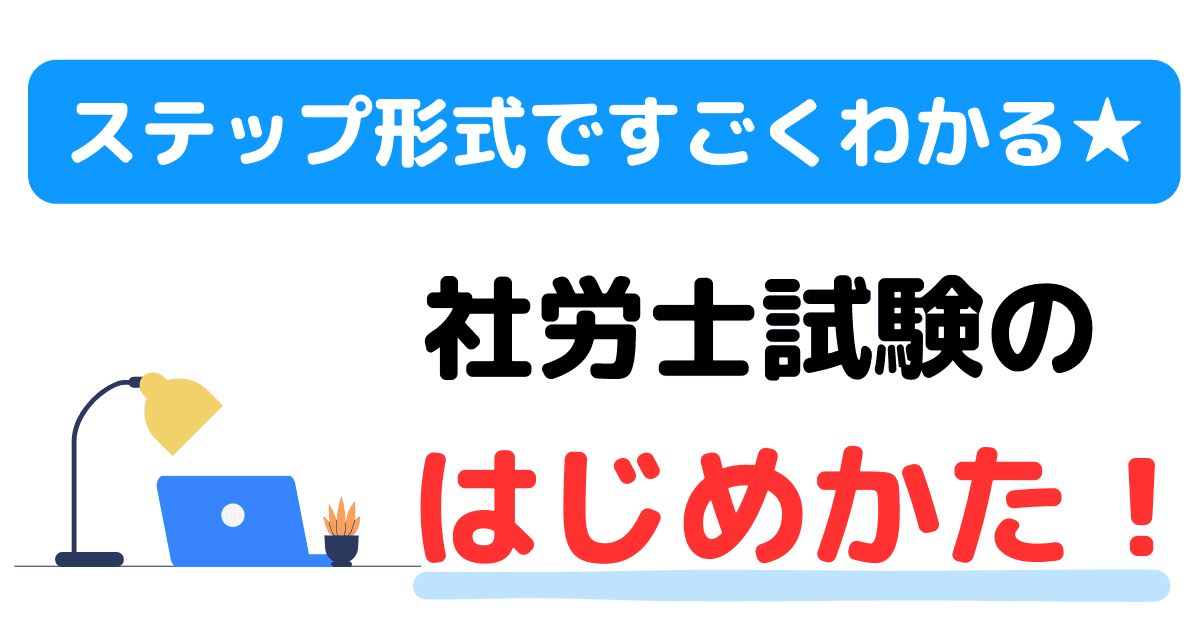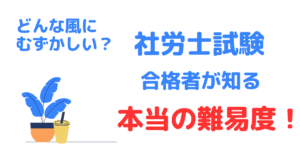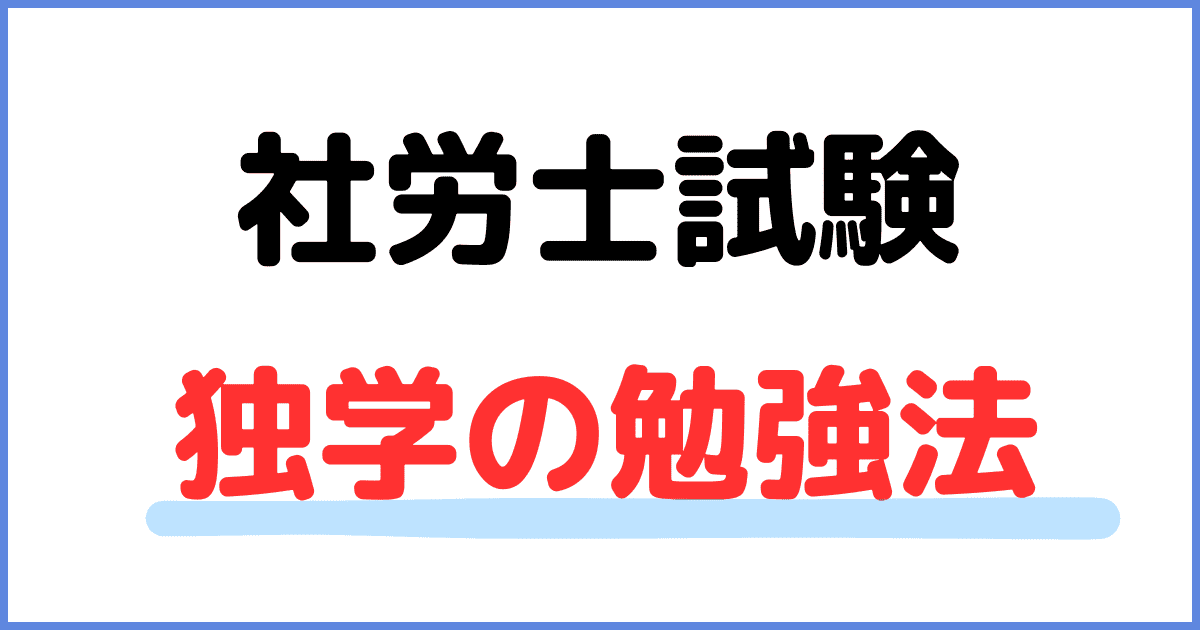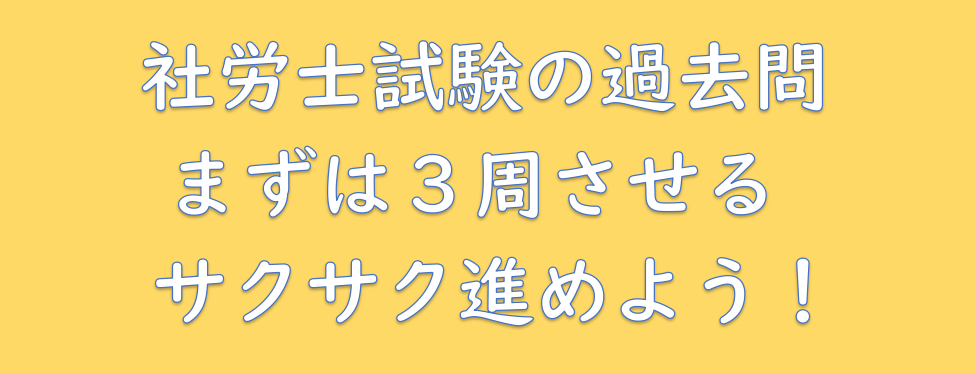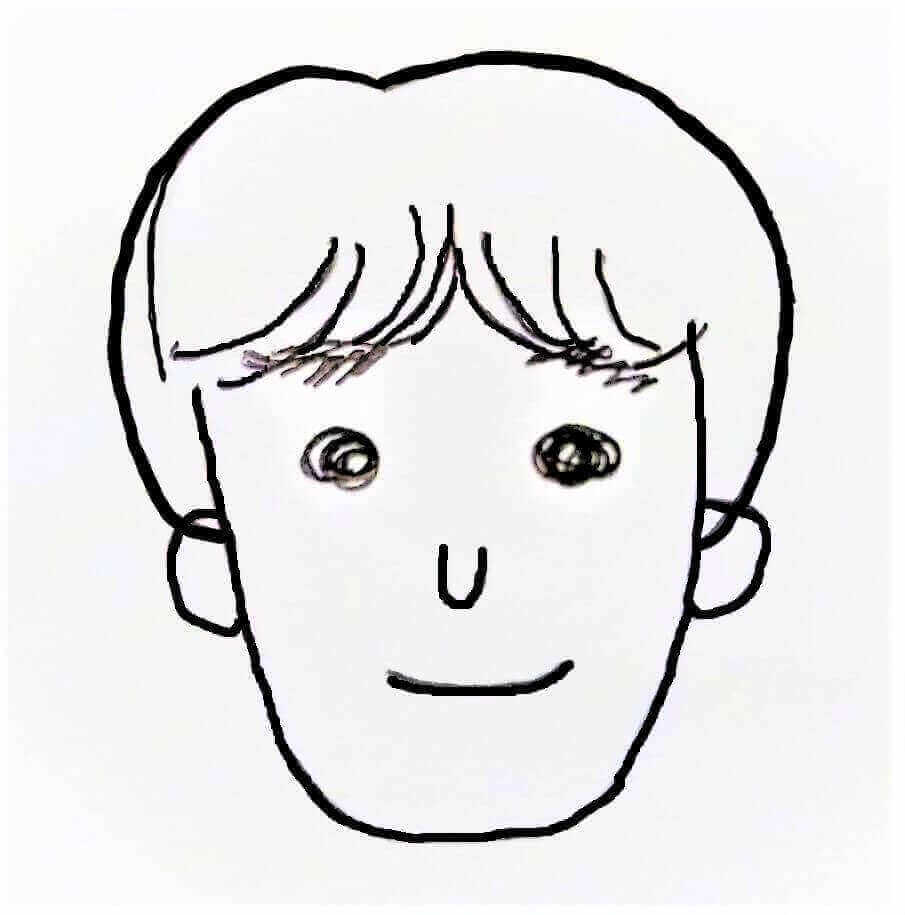- 社労士試験の過去問は、まずは3周させよう!

わかること!
社労士試験の過去問は何周させれば理解できるのかな?
この記事を読むと、社労士試験の「過去問は何周」すれば、理解が深まってくるのかがわかります。結論をいうと、過去問は『3周』させることで、全体像が見えてきてかなり理解も進んできます!
社労士試験の過去問は問題数がたくさんあり、理解できなくて不安になってきます。ですが、最初は誰でも不安なので、あせらず勉強してほしいと思います。
まずは、3周を目標にして頑張ってみると、理解してくるのでモチベーションも上がり勉強にも意欲が湧いてきますよ!
択一式の点数が伸び悩んでいる方は、下記を「CHECK」⇩
択一の点数が伸びないならこちら!
-
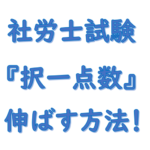
-
【社労士 択一の点数が伸びない!】条文順の過去問で点数を伸ばす
社労士試験の択一が伸びない この記事を書いている私は、社労士試験合格者です。過去問の点数が伸びないなら、当記事をぜひ読んでください。私が実践した「択一の点数を伸ばす勉強法」がわかります! ...
続きを見る
1 社労士試験の過去問は3周まわすと理解ができてくる!
結論、過去問は3周させると理解ができてきます。
3周させれば理解ができてきて、問題も解けるようになるし全体もみえてきます。
過去問を3周させるまでのイメージは、
ポイント
・1周目は「全体像」を把握する
・2週目は「問題を解く」意識
・3周目は「理解して解く」意識
このことを意識して過去問を3周させると、4週目からはかなり理解しながら問題を解けるようになってきます。
それでは、つぎは過去問の1周目と2周目それぞれの勉強方法をみていきましょう。
2 1周目は理解できなくても過去問をドンドン解いていこう!
過去問の1周目のポイントは『全体像をイメージ』することです。
1周目は理解しようとか、問題を解こうと気持ちを焦らさないこと!
はじめは過去問の勉強をしても、1周目はわからないことばかりです。だから問題を解くというよりは、読むという感じでドンドン先に進めてください。
なので、過去問1周目の勉強のしかたは、過去問をテキスト代わりにすること。
ここがポイント!
✓ 過去問題を読む
✓ すぐ過去問の解説をみる
この繰り返しで過去問1周目をさらりとおわらせましょう!
あと過去問1周目はわからないことがあっても先に進むこと。
過去問の解説を読んでどうしてこの答えなの?と思っても、
ココがポイント
その疑問は2週目、3周目と勉強するうちにわかってくるので焦らなくてもいい!
過去問1周目はこのくらいの気持ちのほうが勉強を続けられます。はじめから深追いすると、わからないことばかりで勉強するのが嫌になってしまうかもしれません。
だから、まずは1周目をサクッとおわらせましょう!
勉強なのに答えをみて問題を解くのは、はじめは抵抗があるかもしれないけど、まずは社労士試験の出題形式になれるほうが効率的です!
3 2周目はテキストと過去問のリンクで理解しながら解こう!
過去問の2周目のポイントは『問題を解く・そして理解する』ことに意識することです。過去問を1周させて2週目となると、全体のイメージは何となくわかってきます。
それでも2週目といっても、1回解いた問題でもまちがえることが多いはず。だけど、2周目はまちがえてもいいから実力で『問題を解く』ことです。
そして、まちがえた問題はテキストで確認して『理解』することが大切になります。
ここがポイント!
✓ 過去問でまちがえた問題をテキストで確認
✓ あとはこの繰り返しで2週目をおわるまで続ける
過去問で解いてまちがえた問題があれば、
ココがポイント
テキストで確認する、テキストを確認したら、過去問をまた解く
この繰り返しで、2周目もおわるまで過去問を解いていきましょう!あと、テキストで確認するとき『さらっと読む』くらいで十分です。
過去問でまちがえて、テキストに戻り深読みしてしまうことがあります。ですが、問題を解いているときに、テキストをじっくり読んでいては時間が足りない。
テキストをじっくり読み込むというよりは、
注意ポイント
過去問でまちがえたところをテキストで確認する程度にすること
2周目はテキストと過去問で相互に確認することで、1周目のときより理解をしながら問題を解くことができます。さらに全体のつながりも見えてくるので、3周目となれば理解しながら過去問を解けるようになってきます!
私も、過去問は3周目から理解してきて、さらに2周させたことで全体像が見えてきました。
実体験から過去問の学習は、スピード感を持って繰り返し学習すること、このことが知識の定着にすごく大切だと感じました。
4 まとめ(まずは過去問は3周まわそう)
ここまで、社労士試験の過去問の解き方をまとめると、
過去問は3周まわそう!
・1周目は理解できなくても全体像をつかむため過去問を解く
・2周目はテキストと過去問のリンクで理解しながら解く
・そして3周まわすとかなり理解ができてくる!
ポイントは、過去問は1周目からすべて理解しようとしないで、まずは全体を通して問題を解き切ること!そして、2周目からテキストと過去問をリンクさせ、1回目より理解しながら問題を解く。
このように過去問は段階的に内容を濃くし、少しずつ理解を深めていきましょう。そして3周目には、かなり実力もあがり理解しながら問題を解けるようになっています。
まずは、社労士試験の過去問は3周まわすことを目標に頑張ってみてください。
応援しています!
次は、過去問の一問一答です。特に勉強時間がないという方、下記の記事は役立つ内容になっています。ポイントは「スキマ時間」です!
社労士試験の過去問学習で「一問一答」は、基本知識の定着に効果抜群です!問題形式が一問一答なので、勉強は自宅に限らず「外出先」のスキマ時間を活用できます。むしろ、自宅ではなくスキマ時間を使った学習に最適なのが「一問一答」です。
⇩
過去問一問一答 スキマ時間活用!
-
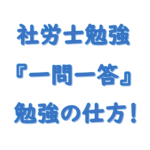
-
【社労士過去問の一問一答!】スキマ時間でおすすめの勉強方法
過去問の「一問一答」はスキマ時間で勉強がおすすめ この記事を書いている私は、社労士試験合格者です。今回は、問題演習の基礎固めとなる「過去問の一問一答」の効率的な勉強法などをお伝えします! ...
続きを見る